ナムルは、韓国人にとって最も伝統的で日常的な食べ物だ。最近ではナムルがメインとなる寺刹料理が広く紹介され、多くの外国人の関心を集め、ベジタリアンの増加とともに高級レストランでもメニューに積極的に取り入れられている。
ドイツのザワークラウト、イギリスのフィシュチップスのように国ごとに代表的な名物料理がある。しかし例えば、メキシコと言えばタコスしか思い出せないからといって、メキシコ料理はそれが全てではない。それはただその人がメキシコ料理についてよく知らないという事実を示すものに過ぎない。
数百年間続いてきた一国の食文化を特定の料理の一つや二つで語るのは難しい。しかし、もし韓国の代表料理としてナムルを選んだ外国人がいたら、その人は韓国料理についてかなり詳しい可能性が高い。

韓国人の食卓に欠かせない春ナムルであるトウルプ(タラノキの芽)、ネンイ(ナズナ)、タルレ(ノビル)(左から)は、早春の野山で採れる。春のナムルは味と香りがよく、冬の間に失った食欲を取り戻してくれる。© gettyimages
韓国料理の真髄
ナムルは、単語自体の意味と用法からして複雑だ。国立国語院の『標準国語大辞典』でナムルを紐解くと、二つの意味が記載されている。一つ目は「人が食べることのできる草や木の葉のようなものをさす言葉」で、例えばコサリ(ワラビ)、トラジ(桔梗)、トウルプ(タラノキの芽)、ネンイ(ナズナ)のようなものがあると説明している。二つ目の意味は、「人が食べることのできる草や木の葉などを茹でたり炒めたり、あるいは生のままで味をつけて和えた料理」とある。
すなわち、ナムルが最初の意味でつかわれる場合には、食材という意味であり、二つ目の意味でつかわれる場合には、調理された料理という意味だ。この時の料理の材料は、辞典的内容よりも範囲が広く、草や木の葉でなくても植物性の材料をナムルのレシピで調理すればナムルになる。その他に草や木の葉とは違う材料が使われる場合では、ジャガイモは塊茎を、ナスは実を使い、それを縦長に切って塩や醤油のような調味料で炒めたり、あるいは茹でて調味料と和えればじゃがいものナムル、ナスのナムルになる。かぼちゃのナムルや大根のナムルも同様で、材料はナムルではないがナムルのように調理した料理だ。
ところで、コンナムル(大豆もやし)のナムルとスクジュナムル(もやし)のナムルは、二つの意味がともに含まれている。大豆や緑豆をカメやザルなどで育てて芽を出した野菜とそれを利用した料理の両方の意味でつかわれるからだ。
季節の料理

春の在来市場では、いろいろな春のナムルをカゴに入れて売っている商人をよく見かける。韓国内で採れる食用の山菜は300種類を越えると言われており、大部分の春ナムルにはビタミンCと無機質が豊富に含まれている。© 聯合ニュース
このようにナムルは、言語自体が複雑な食べ物だ。また「人の食べることのできる草や木の葉」という辞書の説明は短いが、そこには豊富な知識が必要だ。まず食べられるものと食べられないものを区分できなければならない。毒草の若い芽をナムルだと思って間違って食べれば、生命の危機に及ぶこともあり、実際そういうニュースをときどき耳にする。
代表的な季節の食べ物であるナムルは、採集の時期も重要だ。ナムルと言えば春を連想するように、春先の若芽が顔を出し始めるときに食べるものがほとんどだ。植物は成長するにつれ固く丈夫になり、それ以上食用には適さなくなる。もちろん若芽だといって無条件にナムルとして食べられるわけでもない。毒性物質を除去しなければならない場合も多い。タルレ(ノビル)、トルナムル(万年草)、チャムナムル(ミツバ)、チィナムル(シラヤマギク)などは、毒がないので生のままでも食べてもよいが、コサリ(ワラビ)やウォンチュリ(ワスレグサ)のように、必ず火を通して食べなければならないものもある。
その中でもウォンチュリ(ワスレグサ)は、観賞用の植物としても魅力的だが、他の春の山菜よりも甘味とコクがあり、特に早春の若芽はよく食べられている。しかし、ウォンチュリにはコルヒチンという物質が含まれている。コルヒチンは、抗炎症作用があり急性の痛風の症状緩和に薬としても使用される。最近では心筋梗塞後、心血管疾患が発生するリスクをさげる予防薬としても効果的だという研究結果もでている。しかし、ウォンチュリをナムルとして食べる時に、コルヒチン成分を抜かずにそのまま摂取すると吐き気、腹痛、下痢のような症状で苦労することになる。ウォンチュリは成長すればするほどコルヒチン成分の含有量が増えるので、食べられるのは春の若芽だけだ。それも沸騰したお湯で茹でた後に、冷水に十分にさらして水溶性コルヒチンを除去した後に食べないと食中毒の危険性がある。
一方、野山で育つ食用可能な山菜を山ナムルと言うが、韓国に自生する山ナムルだけでも300種類を越える。チュナムル(シラヤマギク)だけでも自生種は60種類に達し、その中で食用として可能なものが24種類だ。このような多種多様なナムルをきちんと楽しむには、いつ・何を・どのように採取し調理すれば安全に食べられるかという知識が必要だ。
さまざまな調理法
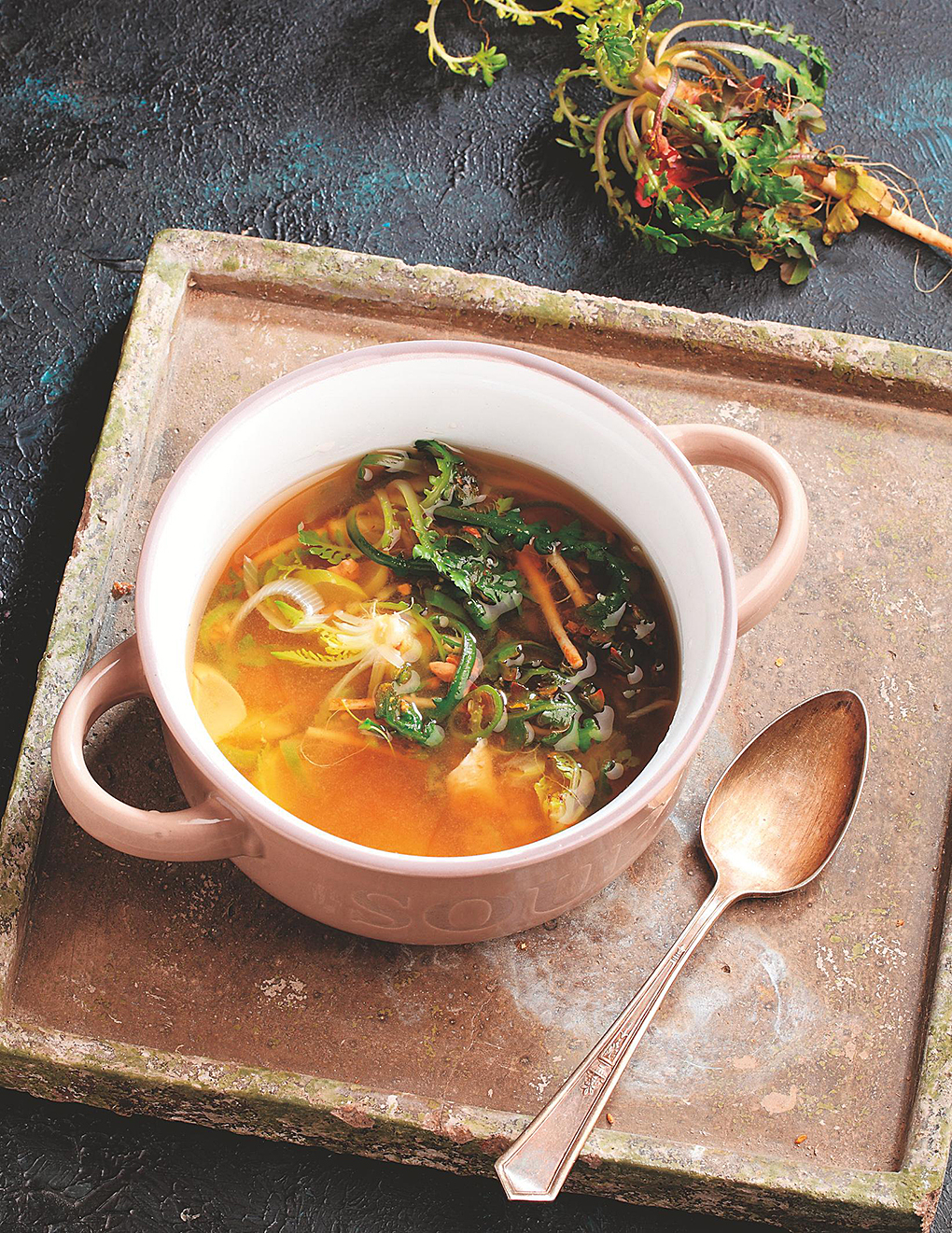
ネンイ(ナズナ)は味噌汁にしたり、茹でて味噌、コチュジャン、ニンニクのみじん切り、ネギ、ごま塩、ごま油などの調味料を入れて和えて食べる。 © gettyimages
ナムルは調理する方法もさまざまなだ。熱湯でさっと茹でるのだが、茹でた後、冷水にさらして苦味を洗い流すのか、炒めるのか、長い間熟成させるのか、醤油で和えるのか、味噌で和えるのか、えごま油を加えるのか、ごま油を加えるのか、あるいはごま塩を振りかけるのか、えごま粉を振りかけるのか、唐辛子粉を混ぜるのか等々を決定しなければならない。そうやって料理したナムルの味と香りは、野の花や草の数ほど実に多彩だ。チャムチナムル(シラヤマギク)は、生のままそのまま食べると青りんごのような香りがするが、茹でて和えるとほろ苦く、噛めば噛むほど芳ばしい香りがする。パンプンナムル(ボウフウ)も基本的に苦味が潜んでいる点では同じだが、ミカンの皮とペパーミントを混ぜたような甘味は、チャムチナムルとはっきり違う点だ。
春のナムルの代表各ともいえるタルレ(ノビル)とネンイ(ナズナ)は、その微妙な味と香りを描写すること自体が非常に難しい。匂いの心理学に対する研究で有名な認知神経科学者のレイチェル・ハーツは、その著書『欲望を引き起こす匂い』で、どんな言語であれ嗅覚経験にだけ限定して使用する単語は、他の感覚経験に限定される単語よりもはるかに少ないと指摘している。タルレ(ノビル)とネンイ(ナズナ)はハーツの説明にぴったり当てはまるナムルだ。食べてから嗅覚の経験を言葉で説明しようとすると言語的な限界を感じる。
タルレは、ニンニクと似たようなアリシンを含有し、ヒリヒリするような味がするが、ニンニクとはまた違ったさわやかな甘味も含んでいる。カラシナ科の植物であるネンイにも黄化合物特有の刺激的な香りがする。しかしこの程度ではネンイの香りを十分に描写しているとは言えない。味噌を入れて作るネンイクッ(ナズナの若葉のみそ汁)は一口、口に含むと、冬の終わりと春の始まりが交差のする日の早朝に、朝露に濡れた土の香りのする野原にたたずんでいるような気分にしてくれる。もちろんタルレやネンイの味については百聞は一見に如かず、どんな説明よりも一口食べるに勝るものはない。

春、タラの木から芽吹いたタラの芽をトウルプナムルといい、主に熱湯をかけてコチュジャンと酢、砂糖をまぜて作った酢コチュジャンで和えたり、つけてたべる。 © gettyimages

ネンイ(ナズナ)は味噌汁にしたり、茹でて味噌、コチュジャン、ニンニクのみじん切り、ネギ、ごま塩、ごま油などの調味料を入れて和えて食べる。© gettyimages
早春の香り
それぞれのナムルを吟味して香りを比較してみることもよいが、コチュジャンとごま油を少し入れて、ご飯の上に半熟卵を乗せてピビンバにして食べても美味しい。ピビンバは、おかずとしてのナムルを用いて誰でも簡単に作ることのできる料理であり、クッパブとともに最も古い韓国の外食のメニューの一つだ。辛くて甘いコチュジャンの味が指揮者のように真ん中に立ち、さまざまなナムルのリズムに合わせて新たなハーモニーを奏でる。
何でも混ぜ合わせて食べるピビンバにたいしては、行儀が悪いとか見た目が悪いなどという批判的な見解もたまにある。しかし、ナムルを知る人ならばピビンバを受け入れるのもたやすいだろう。いろいろなナムルが一つになって誕生するピビンバは、ナムルの多様性と包容の哲学が生み出した韓国料理の真髄だ。
一方、特定地域に行かなければ味わえないナムルも多い。ウルルン島の山ナムルとプジゲンイ(ヨメナ)のように地理的な表示となる山菜に指定されているものもある。最近ではナムルに対する新たなアプローチも活発で、韓国人が最もよく食べる春ナムルの味と調理方法に対する体系的な研究結果を報告書として出している企業もある。またナムルを利用したメニュー開発に力を入れている高級レストランも増えている。そしてナムルは、最も伝統的でありながら革新的な韓国料理となりつつある。